長年放置された土地は高く売れるのか
※このサイトは株式会社フリーダムリンクをスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。
相続してから長年放置してしまっていた土地は高く売れるのでしょうか。当メディア監修の公認不動産コンサルティングマスター永田氏に聞いてみました。
株式会社フリーダムリンク
高値での売却に
期待ができる!

公認不動産
コンサルティングマスター
株式会社フリーダムリンク
永田 博宣
売却を検討している土地が住宅地であれば一戸建てやアパート用地として、商業地であれば商業ビルや分譲マンション用地として買主を探すのがこれまでの一般的な方法でした。しかし、時代の変化とともに土地の利用形態も多様化してきており、高齢者施設やインバウンド向けホテル、投資家・ファンド向けの一棟賃貸マンションなど、今のニーズに合った条件を備えた土地であれば、従来よりも高値での売却が期待できる場合があります。
土地を放置するデメリット
相続した土地や売れない土地を放置すると、さまざまなデメリットが生じます。以下で詳しく見ていきましょう。
固定資産税がかかる
土地を所有している限り、毎年固定資産税や都市計画税がかかります。しかも、空き家も一緒に放置した場合、自治体から「特定空家」に指定され、固定資産税が何倍にもなったり、罰金が課されたりするかもしれません。余計な費用を削減するためにも、早めに手放したほうがよいでしょう。
管理の手間がかかる
放置する期間が長いほど、雑草が生えたり捨てられたゴミが溜まったりするため、こまめに清掃や除草をしなくてはなりません。「手間がかかるから」と管理を放棄すると、荒れ果てて資産価値を大きく下げてしまいます。
所有する土地が遠方にある場合は、さらに注意が必要。継続して管理するには、多くの時間と交通費がかかります。
損害賠償を請求されるおそれがある
放置された土地は、犯罪などのリスクが高まります。大型ごみが不法投棄されたり、野良犬や野良猫、不審者が棲みついたりして、近隣住民に大きな迷惑をかけるかもしれません。トラブルが起こった場合は損害賠償を請求される恐れもあるので注意が必要です。
売れない土地を手放す方法
売れない土地を手放す方法は、大きく分けて「売却する」と「無償で手放す」の2つに分けられます。具体的な方法は、主に以下の3つです。
- 近隣住民へアプローチする
- 地方公共団体(自治体)へ寄付をする
- 相続放棄と相続土地国庫帰属法を利用する
近隣住民へアプローチする
一般的には価値がない、見向きもされないような土地でも、近隣の人には魅力的に映るかもしれません。特に隣家の人なら、現在所有している土地を拡張して駐車スペースを作りたい、二世帯住宅を建てたいと考えている可能性があります。長年売れなかった土地が近隣住民に簡単に売れるケースは意外に多いので、相談してみるのがおすすめです。
地方公共団体(自治体)へ寄付をする
地方公共団体に寄付をするのも一つの手段です。ただし、すべての土地を無条件で寄付できるわけではありません。「公園や公共施設の駐車場として活用できる」など、利用目的に合っている土地に限られますが、可能性として検討してみても良いでしょう。詳しくは、自治体の窓口で確認してみてください。
相続放棄と相続土地国庫帰属法を利用する
相続する予定の土地が売れそうにない場合は、あらかじめ相続放棄をしても良いでしょう。ただし相続放棄では、受け取る財産全てを放棄しなくてはなりません。「現金は相続するけど土地は手放したい」といった選択はできないので要注意です。
すでに相続した土地は、「相続土地国庫帰属法」により国に返却することも可能です。ただしさまざまな要件が設けられており、どんな土地でも対象になるわけではないので注意してください。
資産価値が低い土地でも売れる可能性がある!?
これまで売れなかった土地でも、少し工夫するだけで売れるかもしれません。手放す前にぜひ検討してみてください。
整形して土地の価値を高める
旗竿地や矮小地、複雑な形の土地、広すぎる土地などは、隣地を買い足す・あるいは分筆することで、整形地として価値を高めることができます。費用はかかりますが、結果として高値で売れるかもしれません。費用や売却益などを含めて、客観的に検討してみましょう。
不動産会社の変更を検討する
土地が売れないのは、土地そのものではなく、売り出し方に問題があるのかもしれません。一社に依頼して売れなかったからと諦めるのではなく、不動産会社の担当者や不動産会社自体を変更して様子を見てみましょう。
不動産会社を選ぶ際は、得意分野や対応スピードの速さをチェックするのがおすすめです。対応が迅速な会社は、売却までのスピードも速い傾向にあるようです。
長年放置された土地を売却する際の注意点
不動産会社による囲い込みに注意しましょう
なお、土地を売却する際は「囲い込み」に注意しましょう。囲い込みとは、不動産会社が他社の仲介を断り、自社だけで買主を見つけて売買を成立させようとする行為です。これにより買い手の幅が狭まり、価格が不当に安くなるリスクがあります。売却活動は定期的に進捗を確認し、透明性を確保することが大切です。
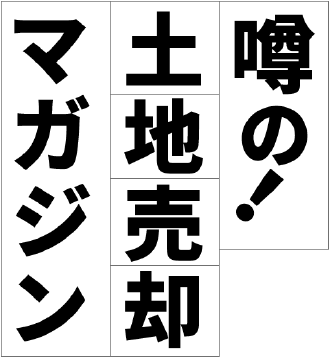
不動産会社選びを慎重にしないと損をするかも
“いつか売る”のつもりが、“ずっと売れない”になっていませんか?放置された土地には、税金・管理・損害賠償といったリスクがあります。今すぐにでも動き出すことが賢明でしょう。ただし、売却を成功させるには、不動産会社による囲い込みといった“目に見えない落とし穴”にも要注意。
当メディア監修の株式会社フリーダムリンクの永田氏解説のもと、不動産会社による囲い込みとは、その対策とコツを詳しくご紹介しています。

