老朽化したアパートは高く売れるのか
※このサイトは株式会社フリーダムリンクをスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。
時代遅れの設備や老朽化が進んで補修費用ばかりかかるアパートは、維持管理の負担が大きくなってしまいます。ここでは、老朽化したアパートは売却できるのか。当メディア監修の公認不動産コンサルティングマスター永田氏に聞いてみました。
株式会社フリーダムリンク
都市部であれば
高く売れる可能性あり

公認不動産
コンサルティングマスター
株式会社フリーダムリンク
永田 博宣
都市部では広めの土地が売りに出されることが少ないため、老朽化したアパートを購入し、入居者との立ち退き交渉から建て替えまでを一手に引き受ける業者が増えています。特に主要駅から近く、土地の面積が大きいなど、活用価値の高い物件であれば、想像以上に高く売却できるケースもあります。そのためには、買主がスムーズに貸主の立場を引き継げるよう、入居者との賃貸借契約書などの書類を整理しておくことが重要です。
老朽化したアパートを売却するタイミング
老朽化したアパートの対策としては、「修繕する」「リフォームやリノベーションをする」「建て替える」「売却する」などさまざまな方法があります。しかし、以下3つのタイミングにある場合、売却を検討するのがおすすめです。
周辺エリアの人気が下がり収益が著しく悪化したとき
まずは、周辺エリアの状況によって入居率が低下、新たな入居者の見込みもほとんどない場合です。周辺エリアの状況は、時代によって異なります。人気がなくなったエリアの老朽化したアパートでは、どんなに家賃を落としても満室経営は難しいでしょう。
入居者募集で物件ポータルサイトを利用している場合も要注意。築年数が経てば経つほど、検索されにくくなってしまいます。入居者側からすれば、できるだけ新しくキレイなアパートに住みたいと考えるのが一般的。賃貸物件を検索する際には築年数で足切りされ、アパートの存在すら知ってもらえない可能性が高まります。
減価償却が終了して税負担が増えるとき
アパートの法定耐用年数は、木造アパートで22年、鉄骨造アパートが27年※と定められており、アパートローンの返済期間や減価償却期間は、この法定耐用年数がもとになっています。
このため、アパートローンを完済した時、減価償却期間が終了して節税効果が期待できなくなった時は、売却を検討するタイミング。売却せずそのまま運用する場合は、建て替えかリノベーションをして経費計上したり、募集条件を緩和したりして、キャッシュフローの悪化を防ぐ工夫をしなくてはなりません。
築年数が40年以上を超えているとき
耐震基準も大きなポイント。1981年5月31日までに建てられたアパートは旧耐震基準に則っており、震度5程度までしか耐えられません。安心して暮らせないアパートでは現代のニーズに合わないため、売却を検討した方が良いでしょう。
老朽化したアパートを売却する方法
耐用年数が経過し、老朽化したアパートでも売却することは可能です。ここでは、少しでも高く売るための2つのポイントをご紹介します。
修繕工事やリフォームをして価値を高める
老朽化したアパートの資産価値を高めることで、より高値で売却できる可能性が高まります。まずはアパート全体の劣化状況を確認し、必要な部分に対して補修・リフォーム工事を行いましょう。一口にリフォームといっても、壁紙の補修や畳の張り替え、ニーズに合わせた設備の交換といった比較的手軽な工事から、屋根・外壁の塗装、屋上防水、給排水管の更新、柱等構造部の補強といった大規模な修繕まで種類はさまざまです。
注意したいのは、むやみに工事費用をかけ過ぎないこと。収益が出る金額を見極めて効果的な部分だけ工事することが大切です。
アパートを解体し、更地にする
アパートを少しでも高く売却したいなら、買い手がすぐに活用できるような状態を目指しましょう。特に築40年以上のアパートは、建物自体の価値がほとんどないため、更地にするのがおすすめです。
ただし、まだ入居者がいる場合はスムーズに退去してもらえるよう交渉しなくてはなりません。また、解体する場合は解体業者に依頼する費用がかかります。木造住宅の解体費用は坪4~5万円が目安※。延べ床面積が30坪の家なら、120〜150万円ほどかかるでしょう。庭木や家財、地中埋没物などを撤去する場合は、さらに費用がかかります。金額は業者によっても異なるため、最低でも2~3社から見積もりを取り、価格や工事範囲などを比較してみてください。
老朽化したアパートを売却する際の注意点
不動産会社による囲い込みに注意しましょう
老朽化アパートを売却する際は「囲い込み」に注意が必要です。囲い込みとは、不動産会社が自社の利益を優先し、他社からの購入希望者を排除して売買を自社で完結させる行為のこと。結果として、買い手の選択肢が狭まり、相場より安く売却されてしまうおそれがあります。売却の際は、販売状況の透明性を確認しましょう。
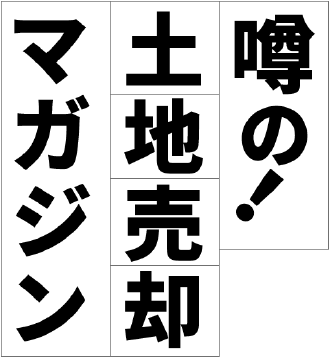
あとは誰に売却するかが肝!
老朽化アパートでも、状況や戦略次第で高く売ることは十分に可能です。修繕・更地化・タイミングの見極め、どれも大切な要素ですが、見逃してはならないのが「誰に売却を託すか」。不動産会社による「囲い込み」が起これば、せっかく整えた売却条件が無駄になってしまうことも。収益物件だからこそ、買い手の幅がカギを握ります。
当メディア監修の株式会社フリーダムリンクの永田氏解説のもと、不動産会社による囲い込みとは、その対策とコツを詳しくご紹介しています。

