相続した土地を売るメリット
※このサイトは株式会社フリーダムリンクをスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。
親や親族から相続した不動産を、特に活用するでもなく持ち続けている人は多いようです。しかし、活用する予定がないのであれば、早めに売却するのがおすすめです。ここでは、相続した不動産を売却するメリットについてご紹介します。
相続税の納税資金の確保ができる
遺産を相続し、正味の遺産総額が基礎控除額を超えた場合、相続税がかかります。相続税とは、財産を相続した人(相続人)が納める税金です。課税対象となるのは、現金・預貯金、有価証券、土地・建物、ゴルフ会員権、貸付金、特許権、著作権、生命保険などです。
相続税には法定相続人1人あたり600万円+3,000万円の基礎控除額が設定されています。例えば、父親に3,000万円の相続が発生し、被相続人が母親と子供2人だった場合、基礎控除額は4800万円(3000万円+600万円×2人)です。正味の遺産額から基礎控除額を差し引いて、総額が基礎控除額以下であれば相続税は発生しません。税務署への相続税申告書の提出も不要です。
ただし、1億円の相続が発生し、同じように被相続人が3人だった場合は、1億円−4,800万円=5,200万円に対して相続税が発生します。
相続税は、被相続人の死亡日の翌日から10か月以内に申告と納税をしなければなりません。相続人が多額の資金を保有していれば問題ありませんが、手元に資金がない場合、相続税を支払うことはできないでしょう。こうしたケースでは、相続不動産を売却して現金化するのがおすすめ。登記上の手続きは煩雑ですが、納税資金を確保することが可能です。
固定資産税など維持費の負担を抑えやすくなる
不動産を所有し続ける限り、毎年固定資産税を払わなくてはなりません。固定資産税とは、毎年1月1日時点の所有者に対して課される税金です。税率は市町村によって異なりますが、標準税率は1.4%※です。
固定資産税評価額は土地の地価や購入価格の70%なので、2,000万円の土地の場合は1,400万円。固定資産税は1,400万円×1.4=19.6万円ということになります。
「1年で19.6万円なら払える」と考える人もいるかもしれませんが、10年、20年と続くと数百万円を支払わなくてはなりません。地域によっては、さらに都市計画税もかかります。雑草の処理や往復の交通費、手間などを考えると、非常に大きな負担ではないでしょうか。しかし土地を売却することで、こうした費用を支払う必要がなくなります。
メンテナンスの手間を抑えやすくなる
使わないまま土地を放置していると、雑草が生えたり捨てられたゴミが溜まったりしてしまいます。荒れ果てて資産価値が大きく下がってしまったら、売却したくても売ることができません。
また、荒れ果てた土地はトラブルの原因になる場合があります。野良猫や野良犬が棲みつく、放火される、不法投棄される、虫が発生するなど、近隣住民に迷惑をかけてしまいます。このためこまめに清掃や除草をしなくてはなりません。
住まいの近くにある場合は通えますが、所有する土地が遠方にある場合は、多くの時間と交通費がかかってしまいます。土地を売却すれば、こうしたメンテナンスの手間を削減することが可能です。
共有によるトラブルを避けやすくなる
相続人が一人しかいない場合は問題ありませんが、財産が土地しかなく、それを数人の兄弟と共有することになった場合は、トラブルリスクが高まります。
共有している土地を活用する場合は、原則として兄弟全員の同意が必要です。しかも二次相続、三次相続が発生した場合は、雪だるま式に共有者が増えていきます。あまりに人数が多い場合は、全員の同意を取ることすら困難です。
こうした状態を避けるためにも、相続した土地は早めに売却するのがおすすめです。相続してからすぐに土地を売却し、そのお金を分割することで、共有状態になった場合のトラブルを避けることが可能です。
譲渡所得税の特例が受けられる可能性がある
土地を売却して利益が出た場合、これに対して譲渡所得税がかかります。しかし相続した不動産については、早めに売却することで、特例措置によって譲渡所得税を抑えることができます。
取得費加算の特例
通常、譲渡所得を計算する際は、財産の売却で得た利益から財産を取得するためにかかった費用を差し引きます。相続財産は本来、取得のための費用は0円ですが、特例を適用することで一定金額を取得費に加えることができます。これにより、税負担を抑えることが可能です。
ただしこの特例は、相続を開始してから3年10ヶ月以内に売却した場合にのみ適用されるため注意しておきましょう。
空き家の3,000万円特別控除
空き家付きの土地の場合は、取り壊して土地を売却することで、譲渡所得から最大3,000万円が控除されます。この特例を利用することで、譲渡所得が3,000万円以下の場合は譲渡所得も譲渡所得税も0円になるのです。
ただしこちらも、相続を開始してから3年以内に売却した場合のみ適用です。また、家屋と土地は相続から譲渡まで空き家状態であること、土地の売却の価格が1億円以下であること、などさまざまな条件があるので要注意。期間を過ぎてしまうと特例措置を受けることができません。
相続する不動産を売却する際の注意点
相続した不動産を売却する際には、税金や契約上のリスクを事前に理解しておくことが大切です。特に注意すべきは、譲渡所得税の負担と売却後に発生する可能性のある契約上の責任です。
想定外の譲渡所得税
譲渡所得税は、不動産の所有期間が5年間を境に税率が大きく異なります。取得から5年以内に売却すると「短期譲渡」となり、所得税・住民税を合わせて約39%の高税率が適用されます。一方、5年を超える「長期譲渡」では、税率を約20%前後まで軽減させることができます。
短期譲渡に該当すると特例を利用できず課税額が増えるので、慎重に売却タイミングを判断するようにしましょう。なお、所有期間は相続が連続しても、最初の取得者が取得した日を起点とします。
祖父が購入し父が相続した不動産を子が相続し売却した場合は、祖父の購入日が起算日です。
契約不適合責任(売却後の責任)
売却後の「契約不適合責任」にも注意が必要です。売却後、たとえば地中に廃材や配管が埋まっていたり境界線が曖昧だったりした場合、買主からの事後的な求めに応じ、売主が責任を負う制度です。
相続した土地は過去の状況を把握しにくいため、売却前に測量や地盤調査を行い、問題の有無を明確にしておくことが望ましいでしょう。相続した不動産の売却に伴う契約不適合責任リスクについては、媒介契約を結んだ不動産会社に詳しく説明してもらうようおすすめします。
売却は相続前と相続後どちらがいい?
相続した不動産を売却する際は、相続前と相続後のどちらで行うかによって負担が大きく変わります。特に税金面と手続き面の違いを把握しておくことが重要です。
まず税金面では、相続前に売却する場合は売主は被相続人本人となり、売却益が出れば譲渡所得税が課税されます。一方、相続後に売却する場合は相続人の所得として扱われ、取得費加算の特例や空き家の3,000万円特別控除など、税負担を軽減できる制度を利用できる可能性もあります。
また、複数の相続人がいる場合での相続後の売却において親族間で意見が分かれた場合、トラブルに発展する可能性を否定できません。一方で相続前の売却であれば、所有者本人の判断で売却を進められるので、分配をめぐる親族間の争いを避けやすいです。
税金面を重視するなら相続後、相続人同士のトラブルを避けたいなら相続前の売却が適しています。
相続した土地・不動産が売れなかった場合
相続した土地や不動産を売りたくても、買い手が見つからずに売却が進まないケースは少なくありません。売却できずに長く放置してしまった場合、固定資産税や管理費用の負担が続くことに加え、雑草の繁茂や建物の老朽化によって近隣トラブルを招くおそれもあります。状況が悪化すれば、行政から指導や罰則を受ける可能性も否定できません。
また、相続人が複数いる場合には、物件の管理責任の所在で意見が分かれて争いに発展するケースもあります。争いが長引けば、上記と同様のリスクにもつながりかねません。
これらのリスクを回避する方法の1つが「相続土地国庫帰属制度」です。一定の条件を満たす土地を国に引き渡すことで、管理や税金の負担から解放される制度です。
ただし、建物が残っている土地や境界が確定していない土地は相続土地国庫帰属制度」の適用される制度です。制度の利用を検討する場合には、まず専門家へ相談してみましょう。
土地・不動産は売るべき?それとも保有すべきか?
売却を検討するケース
- 特例(3年10ヶ月)の期限が迫っている
相続した土地を売却する際には、税制上の特例が利用できる期間に注意が必要です。相続税の取得費加算の特例は相続開始から3年10ヶ月以内に売却した場合にのみ適用される制度となります。
この期限を過ぎてしまうと、税負担が大きくなるだけでなく、取得費加算も利用できません。そのため、結果的には手取り額が減る可能性もあります。
特例の恩恵を受けるためには、売却準備や手続きを早め、進めて期限内に契約を完了できるようスケジュールを立てることが大切です。不動産市場の動向を見極めながらも、早期対応を心がけましょう。
- 共有名義で意見がまとまらない
相続した不動産を親族との共有名義にしている場合、売却や管理の方針が一致しないことを理由に、トラブルへ発展することもあります。
共有名義の不動産では、売却やリフォームなどの重要な決定を行う際、原則として共有者全員の同意が必要なので、一人でも反対すれば手続きが進まず、時間だけが過ぎてしまうこともあります。
話し合いが長期化すると、固定資産税や維持費の負担をめぐる不満が生じ、さらなる関係悪化へとつながるかもしれません。
売却に向けた共有者全員の合意が難しい場合には、自分の持分(共有持分)のみ第三者へ譲渡する方法も検討してみましょう。
保有を検討するケース
相続した土地や建物は、必ずしもすぐに売却する必要があるわけではありません。立地が良く、商業施設や駅からのアクセスが良いエリアであれば、賃貸経営によって安定した家賃収入を得られる可能性もあります。特に人口が多い都市部や再開発が進む地域では、将来的な資産価値の上昇が見込まれる場合もあるため、長期的に保有することで経済的なメリットが大きくなる可能性もあります。
一方で、賃貸経営には空室リスクや建物の修繕費、固定資産税などの負担も伴います。そのため、単に「売る・売らない」で判断するのではなく、収益性と維持コストのバランスを冷静に比較することが大切です。専門家の意見を参考にしながら、保有によるメリットが十分に見込めるかどうかを検討するとよいでしょう。
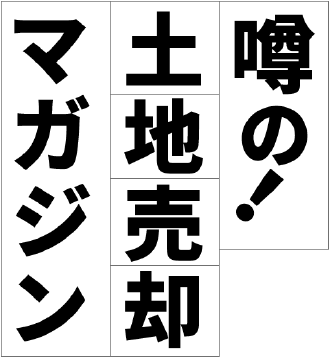
「高く売る」ためのコツも知りましょう
相続税の納税や固定資産税、管理の手間、将来的な共有トラブル…。「売る」という選択肢は、決して後ろ向きではなく、むしろ賢明な判断なのです。
とはいえ、ただ売るだけではもったいないですよね。せっかく売却するなら「できるだけ高く」「どれだけ納得感をもって」売れるかが重要です。当メディアでは「土地を高く売るためのコツ」をわかりやすくまとめています。気になる方はぜひチェックしてみてください。

