相続した土地を売る際にかかる税金
※このサイトは株式会社フリーダムリンクをスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。
相続不動産を売却する際には、主に以下の4つの税金がかかります。ここでは、それぞれの税金の特徴と金額の目安をご紹介します。
- 相続税
- 登録免許税
- 印紙税
- 譲渡所得税
相続税
相続税は、被相続人から財産を相続した場合にかかる税金です。課税対象となるのは、土地や建物、車、現金、有価証券など、金銭に見積もることができる全ての相続財産です。被相続人の死亡によって支払われる「生命保険金」や「死亡退職金」も対象ですが、一定の金額(500万円×法定相続人の数)までは非課税です。
相続税の税率は、遺産総額から基礎控除分や葬式代などを差し引いた額に応じて決まります。基礎控除額は、以下の計算式で算出することが可能です。
基礎控除額:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば遺産総額が5,000万円、法定相続人が2人(配偶者と子1人)の場合、基礎控除額は3,000万円+(600万円×2)=4,200万円。遺産総額5,000万円から4,200万円を引いて、残った800万円が課税対象です。相続遺産総額よりも基礎控除額が多い場合は相続税が発生しません。
登録免許税
相続した土地の名義変更をする際にかかる税金です。税額は土地や建物の評価額(固定資産税評価額)に決まった税率をかけて算出します。税率は登記の種類ごとに異なり、一般的には以下のように定められています。
- 土地の所有権移転登記(売買による移転):2.00%
- 土地の所有権移転登記(相続による移転):0.40%
- 住宅の所有権移転登記(中古住宅を売買により取得した場合):2.00%
- 住宅の所有権移転登記(相続による移転):0.40%
なお、土地だけでなく建物も相続する場合は、それぞれに税金が発生します。
印紙税
契約書や領収書、手形など、売買取引の際に作成する文書に対してかかる税金です。税額は売買代金によって異なります。
- (売買金額が)100万円超500万円以下の場合:2,000円
- 500万円超1,000万円以下の場合:1万円
- 1,000万円超5,000万円以下の場合:2万円
- 5,000万円超1億円以下の場合:6万円
- 1億円超5億円以下の場合:10万円
なお、2027年3月31日までに作成される「不動産譲渡契約書」には印紙税の軽減措置が適用され、売買金額が1億円以下の場合は印紙税が通常の半額になります。印紙税の納付を怠ると、印紙税額の3倍に相当する過怠税を徴収されるので要注意です。
譲渡所得税
相続した土地を売却して、利益(譲渡所得)が出た場合にかかる税金です。譲渡所得の計算式は以下のとおりです。
譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)
譲渡所得税の税率は、土地の所有期間によって異なるので注意が必要です。
- 土地の所有期間が5年以内(短期譲渡所得):30.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%)
- 土地の所有期間が5年以上(長期譲渡所得):15.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%)
例えば、売却代金が1億円で取得費が5,000万円(譲渡費用が100万円)だった場合、譲渡所得は4,900万円です。土地の所有期間が5年以下なら税率30.63%、5年以上なら税率15.315%をかけた額が譲渡所得税です。
所有期間は、被相続人(他界した方)の分も含めて計算します。被相続人が30年所有した土地を相続した場合は、相続後すぐに売却しても長期譲渡所得の税率を適用することが可能です。
譲渡所得税を節税する方法は?
譲渡所得税は、一定の要件に当てはまった場合税制優遇を受けることができます。相続不動産の場合は、こちらの2点に注目しましょう。
- 3,000万円特別控除
- 取得費加算の特例
3,000万円特別控除
相続を行ってから3年以内に土地を売却した場合、そして売却価格が1億円以下の場合は、3,000万円の特別控除を利用することができます。譲渡所得には通常、所得税と住民税がかかりますが、3,000万円を控除できれば、税負担を大幅に軽減することが可能です。
なお、譲渡所得は、売却価格から購入時に要した経費の合計額や建物の減価償却費などを差し引いて計算されます。他の税制優遇と併用することはできません。
取得費加算の特例
相続した土地を売却する場合は、相続税の一部を「取得費」として加算することができます。「相続税が課されている」「土地を相続してから3年10カ月以内に売却」などの条件はありますが、特例を利用することで納税額を減らすことが可能です。
譲渡所得税がゼロになっても確定申告は必要?
譲渡所得税が発生しない場合でも、原則として不動産を売却したときは確定申告を行う必要があります。所得税法上、不動産の譲渡所得は給与などと切り離して計算する「分離課税」に分類されるため、損益にかかわらず申告が求められるからです。
また、確定申告は単なる報告義務にとどまらず、節税特例を受けるための前提手続でもあります。たとえば、譲渡所得を大幅に軽減できる「3,000万円特別控除(空き家特例)」や「取得費加算の特例」などは、確定申告を行わなければ適用されません。
申告を怠ると特例が使えないだけではなく、後から追徴課税や延滞税が課されるおそれもあります。申告期間は売却した翌年の2月16日から3月15日までと定められているので、余裕をもって必要書類をそろえておくことが大切です。
確定申告で必要な書類
確定申告に必要な書類は、どの特例を適用するかによって追加で提出する内容が異なります。基本となる書類はすべてのケースで共通ですが、3,000万円特別控除や取得費加算の特例を使う場合には、自治体や税務署などで発行される証明書類が必要となります。提出漏れがあると特例が適用されないこともあるので、早めに準備を進めましょう。
一般的に必要な書類
相続した不動産を売却した際の確定申告では、以下の基本書類をそろえる必要があります。いずれも売却価格や取得費、本人確認など、譲渡所得の計算と申告内容の裏付けに用いられます。
- 確定申告書:第一表、第二表、第三表(分離課税用)
- 譲渡所得の内訳書:売却価格、取得費、譲渡費用などを計算するための明細書
- 売買契約書の写し:売却時(譲渡時)と被相続人が購入した時(取得時)の両方
- 領収書等の写し:仲介手数料、測量費、印紙税など、譲渡費用や取得費を証明するもの
- 本人確認書類:マイナンバーカードや通知カードの写しなど
2大特例適用時に追加で必要な書類
特例を利用する場合には、上記の基本書類に加えて以下の書類を提出します。事前に市区町村役場や税務署などで取得が必要な場合もあるので、余裕をもって準備しましょう。
①3,000万円特別控除(被相続人の居住用財産)
- 被相続人居住用家屋等確認書(市区町村役場)
- 譲渡所得の内訳書(5面)(税務署/国税庁HP)
- 売却した家屋・土地の登記事項証明書(法務局)
- 耐震基準適合証明書など(家屋が古い場合のみ。更地売却時は不要)(建築士・検査機関)
②取得費加算の特例
- 相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書(税務署・税理士)
- 相続税の申告書控の写し(納税時の控え)
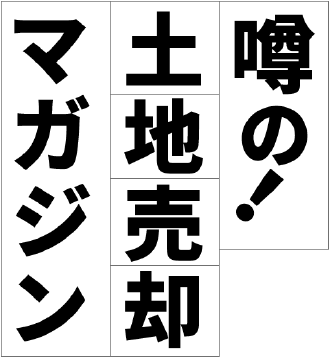
さらに「高く売る」ためのコツも知りましょう
相続した土地を売却する際には、相続税・登録免許税・印紙税・譲渡所得税と、複数の税金が関係する複雑なスキームが存在します。特に譲渡所得税は、特例の活用可否によって納税額に大きな差が生じるため、制度を正しく理解しておくことが重要です。
とはいえ、税負担を軽減できたとしても「そもそもの売却価格」が低ければ、本来得られるはずの資産価値を逃してしまうことにもなりかねません。たとえば、価格設定のアプローチ、買い手への訴求方法、囲い込みリスクの回避など、戦略的な売却術を知っているかどうかで、結果が大きく変わってきます。
当メディアでは、相続不動産を適切に、かつ有利に売却するためのコツを専門家監修のもとでまとめています。

