隣地を買収して活用しやすい土地にして売る
※このサイトは株式会社フリーダムリンクをスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。
隣地の買収することで土地を高く売ることはできると言われていますが、その真相はどうなっているのでしょうか。
当メディア監修の公認不動産コンサルティングマスター永田氏に聞いてみました。
株式会社フリーダムリンク
高く売却できる
可能性があります

公認不動産
コンサルティングマスター
株式会社フリーダムリンク
永田 博宣
特に接道や地型、面積などに課題がある場合、隣地を取得することでそれらの問題が解消されるため、効果が大きくなるでしょう。ただし、隣地の所有者との間で価格や範囲といった契約条件について合意を得るのは簡単ではなく、交渉の難しさが伴います。隣地所有者と話し合える環境であっても、その後の手続きは、土地売却を依頼する予定の不動産会社に相談し、対応してもらう方がスムーズに進むでしょう。
ここでは、隣地を買収して土地を売るメリットと、売却の注意点をご紹介します。
隣の土地を購入するメリットは?
不動産業界では、「隣の土地は借金してでも買え」と言われています。隣の土地を購入するメリットは、以下の3つです。
土地の形状を良くすることができる
隣の土地を購入することで、土地の形状が良くなったり、面積が広くなって活用の幅が広がったりします。
着目したいのが、「増分価値」です。増分価値とは、隣地を購入することで生じる価値の上昇のことです。増分価値は、以下の計算式で算出します。
増分価値=隣地購入後の全体の価格-(自己の所有地の価格+隣地の価格)
例えば、自己の所有地の価格が800万円で、隣地の価格が1,000万円、隣地購入後の全体価格が2,000万円の場合、2,000万円-(800万円+1,000万円)=200万円で、増分価格は200万円となります。隣地の購入によって全体で200万円価値が増え、土地を売却する際も高値で売却できる可能性が高まります。
節税になる
資産を現金で相続するより、土地として相続した方が節税になります。現金は、保有していた額がそのまま評価されますが、土地は「不動産の評価額」をもとに時価より2〜3割程度低く評価されます。このため1,000万円の現金を相続するより、1,000万円で土地を購入し、評価額800万円で評価された方が節税につながります。
遺産の額が大きくなる可能性がある場合は、節税目的で隣地を購入してみても良いでしょう。
隣の土地を購入したほうが良いケース
元々所有する土地が狭小地や旗竿地、道路に面していない土地、複雑な形状の土地である場合、隣地を購入するのがおすすめです。
これらの土地は一般的に売れにくいと言われています。このため隣地を購入して形を整え、「接道状況が良い土地」「日当たりが良い土地」「正方形に近い土地」にした方が、活用の可能性を広げることができます。
ただし、隣地を購入することで面積が広大になる場合は要注意。広すぎて逆効果になる可能性があるため、不動産会社とよく相談してみてください。
隣の土地を購入するときのポイント
隣の土地を購入する際は、いくつか注意したいポイントがあります。以下で詳しくご紹介します。
交渉が難航する場合がある
どんなにこちらが「購入したい!」と思っても、タイミングよく売りに出なければ交渉は難航してしまいます。今は活用していなくても、代々受け継いでいる大切な土地で、売却を考えていないかもしれません。また売却の意思はあっても条件交渉などが長引く可能性もあります。
購入までに数ヶ月から数年かかることもあるため、長期的な視点で計画を立てることが大切です。
隣地の状況を確認しておく
隣地(建物)の所有者、抵当権の設定状況、建築制限などを確認しておきましょう。抵当権が設定されている場合は、所有者が土地を担保に借金をしているため、購入のハードルが高まります。また、建築制限などがある場合は、せっかく隣の土地を購入しても新たな建物を建てられないかもしれません。
購入後のトラブルを避けるためにも、売買交渉をする前にしっかりと調査するのがおすすめです。
あまり無理をしない
いくら不動産業界で「借金をしてでも買え」と言われていても、客観的なメリットがない場合は購入しない方が良いでしょう。国土交通省の「土地総合情報システム」などで土地の相場を把握した上で、購入価格の上限を決めてください。
売り手が想定以上の単価を提示してきた場合は、無理して大きなリスクを背負う必要はありません。自分一人で判断が難しい場合は、不動産鑑定士などの専門家に相談してみても良いでしょう。
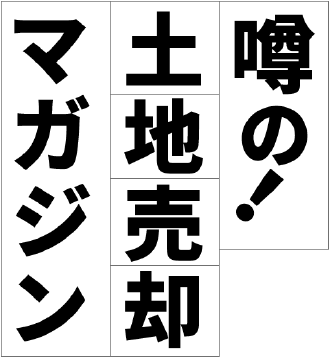
売却時の不動産会社による土地の囲い込みに要注意!
隣地の購入は、土地の価値を底上げし、将来的な売却益にもつながる“戦略的な一手”。ただし、いくら形を整えても、その後の売却戦略が甘ければ、その努力は水の泡です。実は、不動産会社による「囲い込み」が価格を左右してしまうことも少なくありません。
当メディア監修の株式会社フリーダムリンクの永田氏解説のもと、不動産会社による囲い込みとは、その対策とコツを詳しくご紹介しています。

