広い土地分けることで高く売れるのか?
※このサイトは株式会社フリーダムリンクをスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。
広すぎる土地は「活用しにくい」「価格が高い」などの理由で売れにくい場合があり、土地を切り分けて一部だけ売却すると高く売れると言われています。その真相を、当メディア監修の公認不動産コンサルティングマスター永田氏に聞いてみました。
株式会社フリーダムリンク
土地を高く売ることと
あまり関係ありません

公認不動産
コンサルティングマスター
株式会社フリーダムリンク
永田 博宣
宅建免許を持たない個人が、不特定多数に対して土地を分割し、繰り返し売却することは法律上できないため、実際には切り分けた土地の売却相手は通常1組(または1社)に限られます。切り分け方を工夫することで高く売れる可能性を検討できる場合もあるかもしれませんが、「土地を分けて売る」こと自体が価格を上げる手段になるとは限らない、という点には注意が必要です。
以下では、一部だけ売却する方法と、費用目安などをご紹介します。
土地を分割する「分筆」について知ることから
一つの土地を複数の土地に分ける手続きを分筆と言います。土地は一筆、二筆と数え、一筆の土地ごとに登記簿が作成されます。反対に、複数の土地を一つの筆にまとめることを「合筆」と言います。
土地を分筆する主なケースは、以下の通りです。
- 土地の一部を売買するとき
- 土地の一部の地目が異なるとき
- 一筆の土地を複数の相続人で分けるとき
- 一部の土地に抵当権をつけたいとき
注意したいのが、一般の人が複数の土地を売ることは、宅地建物取引業法違反となる恐れがあることです。このため一つの土地をいくつかに分筆し、複数売却することはできません。土地の一部だけ分筆して売却し、残った土地を自身の住まいとするなど、土地活用の方法を考えましょう。
分筆の流れ
分筆の手続きは、一般的に以下の流れで行います。
- 土地家屋調査士に依頼する
- 法務局、役所などで調査・資料収集する
- 現地確認
- 分筆案の作成
- 測量および資料との照合
- 現地立会
- 境界標の設置・確定図の作成
- 登記申請
土地を分筆する際は、土地家屋調査士に依頼をします。依頼を受けた土地家屋調査士が法務局・役所で調査や書類収集などを行ってくれます。書類とは、登記事項証明書、公図、地積測量図、確定測量図などです。
手続きの中で特に重要なのが、現地立会です。役所の担当者や隣地土地所有者が立会い、隣地との境界を決定します。多くの場合はスムーズに進みますが、中には両者の主張が食い違い、境界線を決められない場合もあるようです。また、隣地の所有者自体がわからない、というケースもあります。この場合は「筆界特定制度」を利用して筆界特定登記官に境界線を特定してもらうことができます。
現地立会が終わったら、境界標の設置・確定図を作成して、必要な書類を法務局に提出。登記済み証を受領したら、手続きは全て完了です。
分筆費用の目安は
分筆にかかる費用は、主に土地家屋調査士へ支払う報酬、法務局に収める登録免許税の2つです。土地家屋調査士の報酬は依頼内容によって異なります。一般的に境界が確定している場合は10万円〜、測量図や境界確認書などがなく、一から境界を確定させる場合は30万円~80万円ほどかかります※。
登録免許税は1筆ごとに1,000円です。分割する土地の筆数だけ登録免許税がかかるため、2筆に分筆する場合は2,000円、3筆に分筆する場合は3,000円がかかります。登記申請の代行を依頼する場合の費用は6万円ほどです。
分筆にかかる期間は
分筆にかかる期間も、境界が確定しているかどうかで大きく異なります。境界が確定している場合は1ヶ月以内ですが、確定していない場合は数ヶ月、あるいは1年以上かかる場合があります。境界トラブルが発生して訴訟まで進んだ場合は数年かかる可能性も。このため、分筆を行う場合は余裕を持って計画を立てることが大切です。
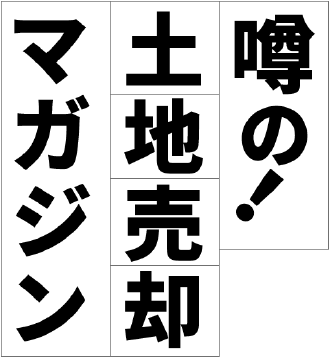
売却時の不動産会社による囲い込みに注意!
土地の分筆は、売却や活用の可能性を広げる有効な手段。ただし、境界確認の手間や手続きの複雑さには注意が必要です。さらに見落としがちなのが、せっかく分筆して価値を高めても、不動産会社の囲い込みで思うように売れないケースがあるということ。
当メディア監修の株式会社フリーダムリンクの永田氏解説のもと、不動産会社による囲い込みとは、その対策とコツを詳しくご紹介しています。

